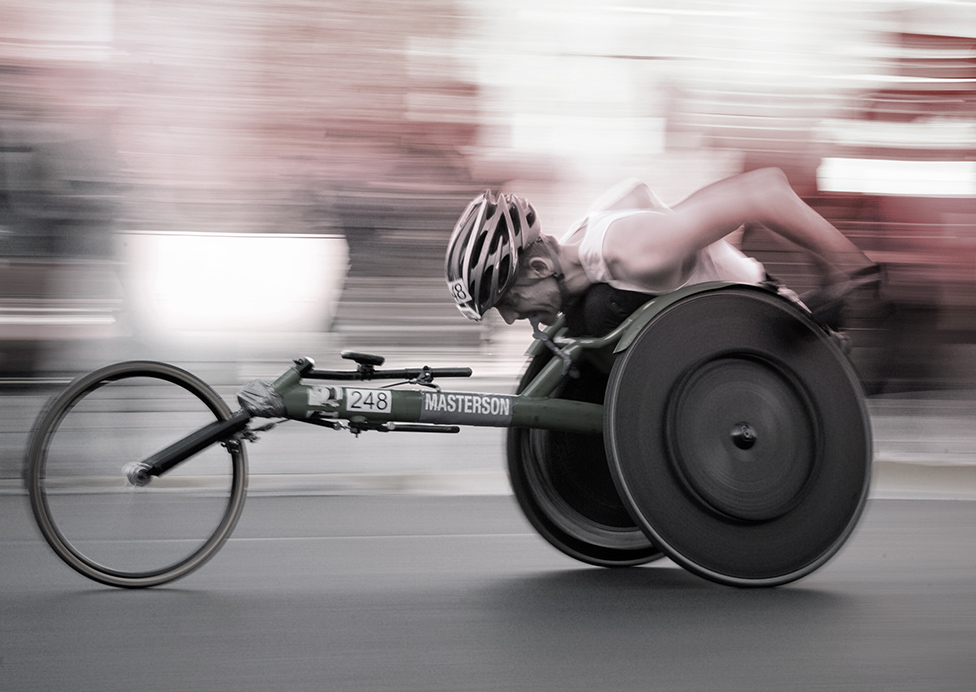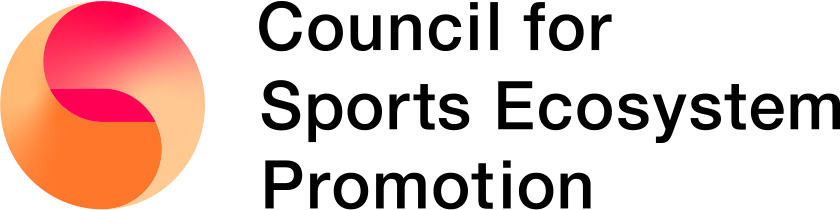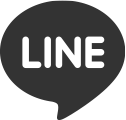第1回 part1:
学校部活動の地域展開の今を知る。
石塚大輔氏(スポーツデータバンク株式会社 代表取締役)
第1回目、学校部活動の地域展開の今を知る。
ながらく日本における次世代のスポーツを担う子どもたちがスポーツと出会う場として最初にその門戸を叩くのは学校の部活動でした。しかし、人口減少と教職員の労働環境の改善といった観点から、学校での部活動を地域展開していくという流れが生まれています。地域のスポーツに、エコシステムの必要性が求められる中、その最先端を走る石塚氏(スポーツデータバンク株式会社代表取締役 一般財団法人スポーツエコシステム推進協議会幹事 マネジメント支援委員会副委員長)にお話を伺いました。
___ 早速ですが、昨今なぜ「学校部活動の地域展開」が必要とされるようになったのでしょうか。
この動き自体は、平成29年度(平成30年3月)に文部科学省スポーツ庁が「運動部活動の在り方に関する総合的なガイドライン」を策定したことから始まっています。このガイドラインでは、「平日は1日休み、土日はどちらかを休みにする」「週休2日を確保する」「平日は2時間、休日は3時間まで」という活動日数や時間の目安が明記されました。「今後、部活動が地域と連携していくことが必要」という一文が入っており、これが部活動の地域展開の背景にあるのだと思っています。
それ以外にも令和2年には、文部科学省スポーツ庁から「学校教職員の働き方改革を踏まえた部活動改革に関する通知」が発出されました。この頃から「地域移行」(現在は「地域展開」へ名称変更)という言葉が世の中で広く知られるようになってきました。
当初は、教職員の働き方改革という観点から議論が始まりましたが、最近の調査や実証事業から、教職員の働き方改革だけでなく、人口減少によって子どもたちのスポーツや文化活動の環境が維持できなくなっているという、より深刻な課題が浮き彫りになってきました。
___ 人口減少が子どもたちのスポーツ環境にどのような影響を与えているのでしょうか。
今後10年で中学生世代の人口は約2割減少すると言われています。現時点でも、全国平均で部活動の参加率・加入率は6割を切っており、たとえば沖縄県では5割に迫る地域も存在します。これは、かつて学校ごとに専門的な環境が整っていた時代とは異なり、学校単位で部活動を維持することが難しくなっている現実を表しています。
つまり、「学校単位で行うスポーツ=部活動」という構図が通用しなくなってきているのです。
___ 学校外でのスポーツ環境も変化しているのでしょうか。
そうですね。近年では学校外にクラブチームが増え、部活動に加入しなくてもスポーツができる環境が整ってきています。その影響もあり、特に野球やサッカーといった人気のチームスポーツは、中学生の部活動加入率が著しく減少しています。
一方で、バドミントンやテニスといった少人数で行える種目は、部活動として維持されている学校も若干増えている傾向にあります。
___ スポーツ環境の維持のしやすさに違いがあるのでしょうか。
はい。子どもの数が減る中で、学校単位で維持しやすいのは少人数の種目です。逆に、チームスポーツは多くの人数を必要とするため人数確保が難しくなり、学校単位での運営が困難になっています。そのため、近隣の学校と連携して複数校でチームを作る「合同部活動」という形態が増えており、特に野球やサッカーに多く見られます。
このことから、学校単位でチームスポーツを行うことが限界に来ているという現状が、データからも明らかになってきています。

___ その中で、石塚さんが注目されている子どもたちのニーズの変化とはどのようなものでしょうか。
スポーツ庁の調査や我々が独自で行った生徒へのアンケート調査から、普段スポーツ活動に接していない生徒も含めて、大きく次のような三つのニーズがあることが分かりました。
第一に、「好きなスポーツができればやりたい」「やりたいスポーツがないから入っていない」という声です。
第二に、「自分のペースでできる部活動に参加したい」というものです。ガイドラインで示された週休2日を逆に言えば、週に5日活動するということになりますが、それに対して、もっとライトな形で自分のペースで参加したいと考える層が一定数いることがわかりました。
第三に、「様々なスポーツを体験してみたい」という、いわゆるマルチスポーツへのニーズです。これは、一つの競技を極めるというよりも、さまざまなスポーツに触れてみたいという子どもたちの欲求を表しています。
このような多様なニーズの存在こそが、現在の部活動の地域展開における象徴であると感じています。
___ 多様なニーズがある一方で、学校現場にはどのような課題が生じていますでしょうか。
最大の課題は、教職員の負担です。体育の専門教員でもなく、競技経験もない教職員が部活動の顧問を務めているケースは少なくありません。ニーズが多様化していく中で、すべてを教職員だけに委ねるのは非常に困難です。
こうした背景からも、学校単位から地域単位へと運営の枠組みを見直す必要があると考えています。
まとめると少子化で人口減少が加速することによって、1つの部活動あたりの参加人数が減って、学校単位での活動が難しくなる。例えば、野球をやりたかったとしても野球部がない中学校が全国で多くなり、やりたいスポーツが選べない、それによって体験機会を失ってしまう事態が発生しているということが、部活動の地域展開を推し進める大きな要因だと思っています。
___ 学校部活動の地域展開において、特に注視すべきポイントは何でしょうか。
これまでのように、学校単位で教職員が指導するという従来型のモデルをそのまま維持することは難しくなっています。そこでまず必要なのは、運営単位を「学校」から「地域」へと拡大することです。
市町村単位、あるいは小規模自治体であれば近隣の市町村同士が連携するなどして、「地域」を定義し、その中で必要な地域クラブを立ち上げていくことが考えられます。
その際、専門的な指導ができる人材が地域にいれば、兼職・兼業の制度を活用して地域のスポーツ活動や文化活動に携わることも可能です。
また、スポーツをする子どもたちには、「技術を高めたい層」と「楽しみとして体験したい層」が存在し、それぞれに必要な指導者像が異なります。競技経験を活かした専門的なスキルが求められる前者に対し、後者では安全・安心な環境を整えられる指導者の存在が求められます。地域の規模や属性に応じて、それらをきめ細かく設計する必要があります。
___ 地域とスポーツをつなぐ事例として、何か参考になる動きはありますでしょうか。
例えば、オリンピックで注目されたスケートボードは、全国各地にスケートボードパークが新設されるなど、環境が整備されてきています。このように、地域政策と地域クラブ活動が連携することで、スポーツや文化を軸とした地域発信も十分に可能です。
つまり、教職員の負担軽減や子どもたちのスポーツ環境の整備にとどまらず、地域のまちづくりとしてスポーツや文化活動の環境を再設計する視点が極めて重要です。自治体の政策と一致させることも大事な目線だと思います。

___ 地域展開を進めるにあたって、既存の学校施設をどう活用していくべきでしょうか。
世界的に見ても、日本ほど学校単位で体育施設が充実している国は他にありません。全国の公立中学校は約9,000校あり、それぞれに体育館やグラウンドが備えられています。これらを地域資源としてどのように活用していくかは、今後の鍵となります。
教育委員会の多くは部活動の地域クラブ化を検討していますが、これに不可欠なのが施設の在り方や活用方法に関する議論です。現在の施設は学校ごとに管理されており、管理権限は学校長など学校の内側にあります。
これらの施設を地域に開放し、より多くの人が参加できるようにするためには、施設の“コミュニティ化”が必要です。同時に、将来的な人口減少に対応するには、大型施設を新設するのではなく、既存の体育館やグラウンド、教室といった機能を分散させて活用するという視点も重要です。
たとえば、防音設備の整った音楽室や調理室などを休日・夜間も地域に開放することで、多様なニーズに応えられる可能性があります。一方で、学校関係者の外部の人が学校に出入りすることへの不安もありますが、顔認証やAIカメラなどICTを使ったセキュリティ対策を導入することで、解決可能と考えています。
___ こうした施設整備には予算確保が欠かせないのですが、国の政策もしくはスポーツ庁での予算措置はどのように検討されているのでしょうか。
令和7年度のスポーツ庁予算では約40億円が計上され、国の政策としても進んでいます。その一部は、地域クラブ化に向けた設備投資や実証事業に活用可能です。
___ 具体的にはどのような使われ方をされているのでしょうか。
スマートロックやセキュリティ設備の導入、クラブ運営のための予算などが検討されており、制度の使い方次第では多面的な活用が期待できます。
部活動の地域展開は、「まちづくりの一環」として位置づけられており、教職員の働き方改革にとどまらず、子どもから高齢者まで地域住民すべてがスポーツや芸術文化に触れるきっかけを生み出し、ただ競技力向上だけじゃなく、例えば健康促進といった意味でライフパフォーマンスを向上させるための視点も大事だと思っています。

___ 地域クラブ化において課題となる「指導者不足」については、どのようにお考えでしょうか。
よく耳にするのは、「教職員に代わる指導者がいないので難しい」という声です。しかし、私はまず「どのようなレベルの、どのような種目に、どのような指導者が必要なのか」という要件を細かく定義することが重要だと考えています。
つまり、競技経験のある専門的な指導者が必要なケースもあれば、基本的な安全配慮や見守りができれば良いという場面もあるということです。そのような視点から見れば、実は担い手となりうる人材は数多く存在しています。
これを明確に定義した上で募集をかければ、ロールモデルとなる人材を見つけて活動を始めることが可能です。日本では多くの人が部活動を通じてスポーツ活動・文化活動に触れてきた歴史があり、その中から適任者を見つけていくことは十分に現実的だと思っています。
___ 指導者を確保した後、クラブ運営や生徒の管理にはどのような仕組みが必要でしょうか。
制度設計の初期段階では、「財源の確保」や「クラブ運営の方法」「生徒の出欠管理」「個人情報の保護」など、さまざまな課題があります。これらに対しては、アプリケーションなどのICTを活用したシステム導入が効果的です。
また、指導者の安心・安全を確保するためには、研修制度の構築や評価制度の導入も欠かせません。施設の設備整備と連動して、これらをワンパッケージとして設計・検討していくことが、これからの地域クラブモデルには求められていると考えています。
すでに、こうした取り組みを進めている自治体からはさまざまな成功事例が出始めており、それらの知見を活用しながら全国へ広げていくことが可能です。
次回は、学校部活動の地域展開を実現するための具体例とその施策に関してお話を伺っていきたいと思います。
(インタビュアー:大久保 奈美)
石塚大輔(いしづか だいすけ)氏 プロフィール
スポーツデータバンク株式会社 代表取締役
一般財団法人スポーツエコシステム推進協議会 マネジメント支援委員会 副委員長
2003年、スポーツを通じた地域課題の解決と地域活性化を目的として「スポーツデータバンク株式会社」を設立。2016年には「スポーツデータバンク沖縄株式会社」を設立し、台湾にも法人を展開するなど、国内外で事業を拡大。
地域のスポーツ資源を活用し、イベントの誘致や地域クラブの制度設計支援を通じたまちづくり、教育・文化政策に関するコンサルティングを幅広く手がけ、中でも近年は「学校部活動の地域展開」に注力し、制度設計や実態調査、システム導入支援を含む伴走型支援のモデル構築を進め、日本全国の自治体と連携して地域クラブ展開を推進・支援している。
「地域スポーツの価値を再定義し、スポーツを核とした持続可能なエコシステムの構築」をビジョンに掲げ、政策と現場をつなぐ実践的な橋渡し役として活躍。

一般財団法人スポーツエコシステム推進協議会マネジメント支援委員会では、スポーツエコシステムの構築・発展を担っていく人材・組織・ガバナンスが、さまざまな業界との循環を通じて強化されていくように議論・検討を行っています。